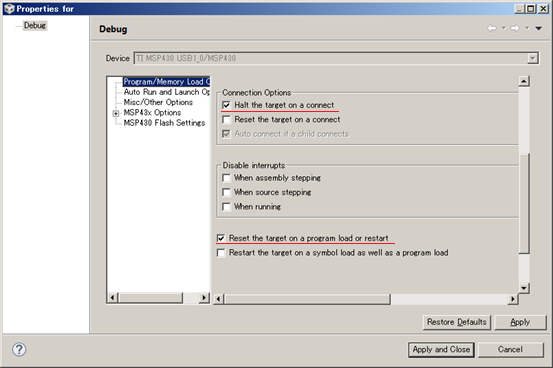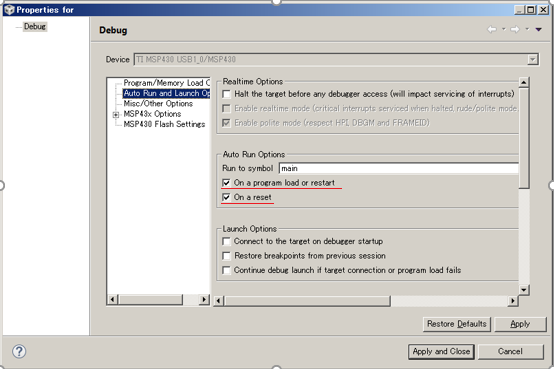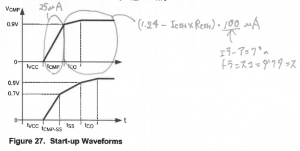-
検索結果
-
TPS62140AのMinimum On-Timeの質問です。
TPS62140AのHigh-side MOSFETのMinimum On-Timeは何nsでしょうか?
FSWpinの設定の参考にしたいと考えております。トピック: エラッタについて
TI製IEEE1394トランシーバ(TSB41AB2)についてご教示願います。
TI社HPにエラッタ情報があったのですが、
エラッタを要約すると、
“データ転送中にアンプラグか電源OFFするとノードがロック(動作不可)される”
という理解で正しいでしょうか?TSB41AB3、TSB43AB22という製品も使用しているのですが
これらも同じエラッタが適用されるという理解で合っていますか?トピック: TLV7041の入力定格について
TLV7041DCK(コンパレーター)を弊社機器外部信号入力ラインの初段への使用を検討しています。
TLV7041データシートの絶対定格欄に、
Input pins : min Vee-0.3V、max 7V
とありますが、ICに電源が入っていない(=0V)の状態に、
入力端子に7V未満,0V以上の電圧が入力されてもICは破損しないという認識でよろしいでしょうか。(尚、Vee=0V)以上ご回答よろしくお願いします。
トピック: Operating currentについて
データシートP.5 DRIVER SUPPLY
IVDD.opにつきまして。下記条件の場合の電流値を教えて頂けないでしょうか。
・VDD=12V, fsw=100kHz, RDRV=15Kohm, 50%duty
・VDD=12V, fsw=100kHz, RDRV=15Kohm, 100%duty
データシートP.7 にあります、
Figure 6. VDD Supply Current vs Switching Frequencyを確認すれば良いでしょうか。以上どうぞ、よろしくお願いいたします。
毎度お世話になります。
早速ですが、LAN-PHY 「DP83822IRHBR」の
データシートP.11「7.6 Timing Requirements, Power-Up Timing」に関してご教示を戴きたく
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822h.pdf「T2 Post power-up stabilization time prior to MDC preamble for register accesses 」ですが、
リセット解除から200ms以内にMDCのアクセスが必要との認識で良いでしょうか。また、ハードウェア構成のラッチ時間「T3 Hardware configuration latch-in time for power up」
がtyp 200msとなっているため、T2はT3よりも後になるようにする必要があると考えておりましたが間違いでしょうか。以上どうぞ、よろしくお願いいたします。

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page