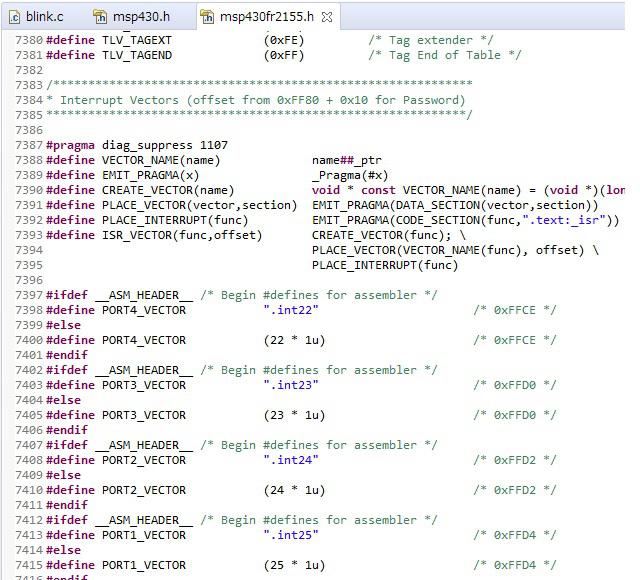-
検索結果
-
トピック: MSP430のノイズ耐性
現在、TI製マイコンを搭載した製品にてノイズ耐性が弱いことがわかり、対策を行うため調査中です。
対象のマイコン:MSP430FR6989IPZ (TI製)
現状で、JTAG用端子のTESTピンに静電気を印加すると消費電流が増加する不具合となります。
JTAGモードがONになるということでしょうか。
この現象はMSP430シリーズすべてで発生する現象でしょうか。
あるいは同じシリーズでも静電気ノイズ耐性が強いものがあるのでしょうか。
また、消費電流が増加した状態では電池寿命には影響しますが、その他の機能には
影響はないと考えていますがいかがでしょうか。
他の製品にもMSP430シリーズのマイコンを使用しており、確認したいです。
急で申し訳ありませんが、今週中(11/19)にご回答を頂きたいです。(早い方がいいです)トピック: ベクタアドレスの記述について
添付ファイルの様に、割り込みソースとベクタアドレス(C言語上記述)が一覧となった表はありませんでしょうか?
ユーザーズマニュアルなど探してみましたが、Word Addressとなっていました。
よろしくお願い致します。トピック: バス制御端子について
バス制御端子について質問させて頂きます。
バス制御端子の内、RNW(read not write)とOE(output enable)は
意識的にどの様に使い分けを行えば宜しいでしょうか?また、WEを含めバス制御端子は同時に動作可能でしょうか?
他のデバイスにてロジックを組んで16bitバスのUB,LB信号を
生成しようと考えております。トピック: SN74AHC1G08について
SN74AHC1G08について
データシート1ページ目にて以下の記載があるのですが
Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall TimeVIH、VILで規定しておりヒステリシス電圧の記載もなさそうなのですが
シュミットトリガとして使用できるのでしょうか(ヒステリシス電圧ありましたら教えていただけないでしょうか)以上、よろしくお願い致します。

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page