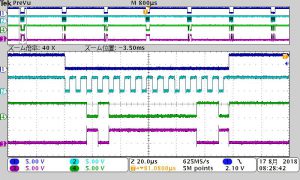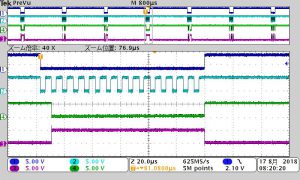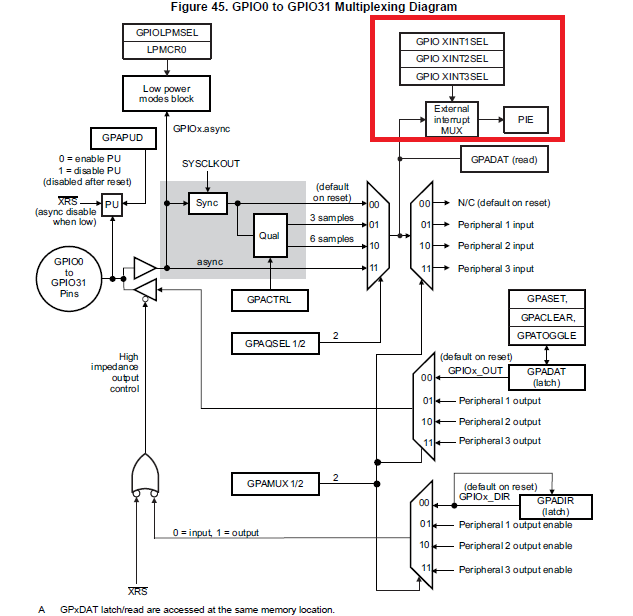-
検索結果
-
トピック: ADS7822の動作について
添付「波形1」が正常時です。「波形2」がNG時です。
NG時は6ピン DOUT (CH4)が”L”一定で変化しません。
推定原因を御教示願います。
波形の各CHは下記を測定したものです。
CH1:5ピン CS/SHDN
CH2:7ピン DCLOCK
CH4:6ピン DOUT
(CH3は6ピンの反転信号です)トピック: MAX3232ECDRについて
MAX3232ECDRを使用する場合の外付けコンデンサの推奨値が添付データシート
の10ページ目に 記載しておりますが、これらのコンデンサについて
必要な耐圧をご教示願います。念の為の確認ですが、MAX3232ECDRのデータシート10ページ目
【9.2Typical Application】に記載されていますC3の接続についてですが
図ではV+端子~GND間にC3を接続しております。これについて、GNDの代わりにVcc(+5V)に接続しても問題ないと言う
認識で宜しいでしょうか?
(同ページの(1)の内容より、そのように認識しております。)【DS14C232CMX】を搭載しいる現行基板で該当コンデンサはV+端子~Vcc(+5V)間
に接続しております。MAX3232
http://www.tij.co.jp/product/jp/MAX3232DS14C232(既に廃盤のようなので見つからず別のSiteのURLとなります)
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/DS14C232_Rev2013.pdf急で申し訳ございませんが、至急回答頂けると助かります。
トピック: LMT87について
ご担当者 様
LPMパッケージ(リードフォーミング品)を検討しておりますが、以下確認させて
頂きたくお願い申し上げます。LMT84~87の違いは出力電力のみであるという認識でよろしいでしょうか?
入力電圧は全部5.5Vまでですので、基本的には全部同じものと思われますが、
ゲインに若干の違いが有るようですが、これは単純にユーザーの電源電圧の
違いに対応したものということでしょうか?また別件でLMT87のLPGパッケージとLP(LPMも含め)パッケージは温度の
検出能力に相違はございますか?LPパッケージの方が大きいので、サイズにより違いがあればご教示頂けま
したら幸いです。以上お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page