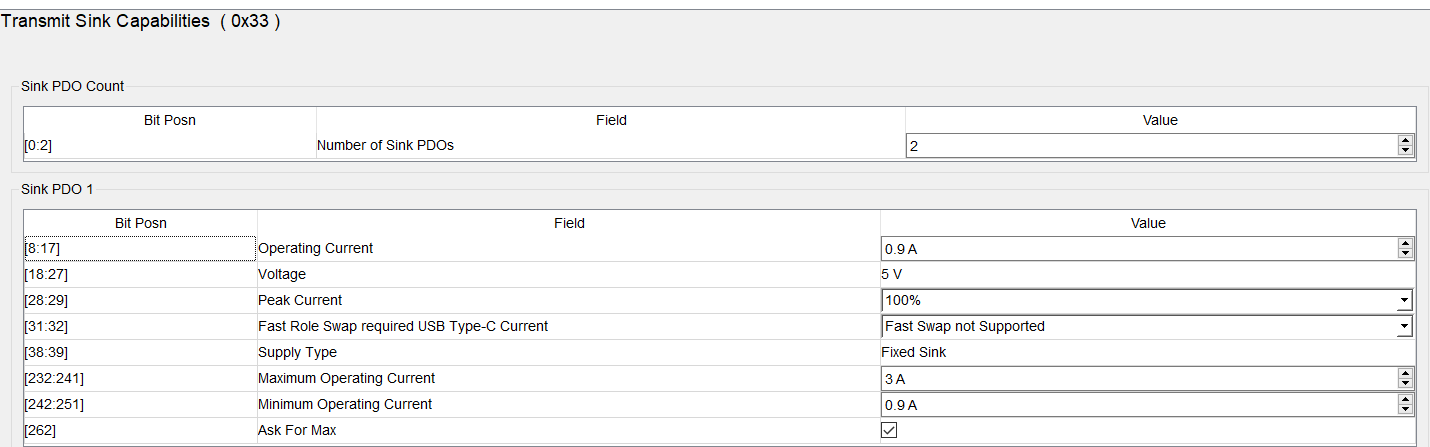-
検索結果
-
いつもお世話になっております。
以前WEBNCHにてLM5116を使用して入力16V~24V、出力12V/10Aの回路を作成しました。
詳細の動作を確認しようと本日、PSpice for TI 2020をインストールして回路図を作成しましたが出力は0Vのままでした。
もしLM5116のPSpiseサンプルデータがありましたら頂けないでしょうか?
シミュレーション結果が見れるデータから修正すれば、動作するのではないか?と思われます。
ご確認の程よろしくお願いいたします。トピック: TPS6590379のpower upについて
TMDXIDK574の回路図をbaseに、ARMプロセッサのAM5749を使用した回路を
設計しようとしております。
AM5749用の電源を生成する為、TPS6590379を使用しようとしておりますが、
2点質問があり回答をお願いします。(1)TPS6590379の起動について
TMDXIDK574では、TPS6590379はCPUとI2Cをはじめ制御信号で接続しており
また押しボタンスイッチのSW3が接続しておりますが、
CPUより制御したりSW3を操作しなくても、J1より+5Vを入力すれば、
SLIU011FのFigure9で記載されておりますシーケンスで電源が起動しますでしょうか?TPS6590379を使用した基板を製造し、初めて電源を投入する場合、
TMDXIDK574の構成で設計すれば、I2Cからの設定やSWの操作をしなくても
TPS6590379の入力に+5Vを入力すれば、SLIU011FのFigure9で記載されております
シーケンスで電源が起動しますでしょうか?(2)TPS6590379のPWRONの仕様について
TPS6590379の電源の再起動をPWRONpinを使用して実現しようとした場合、
SLIS165GのFigure5-19より、2度PWRONpinをLowにする必要がございますでしょうか?
また、RPWRONを使用して再起動を実現しようとした場合は、
RPWRONpinを1度Lowにすれば再起動できますでしょうか?トピック: ePWMのハイレゾモードが適用されない
お世話になります。
早速ですが、
今まで、相補モードでPWMAにハイレゾを適用してうまく動作していました。
しかし、プッシュブル出力を得るために、CMPA、CMPBを使用してPWMA、Bを生成しています。
そこに、今回PWMA,Bにそれぞれハイレゾを適用しようと思いますが、設定を変えても変化はありません。
何か関連したレジスタ設定があるのでしょうか、ちなみに添付したファイルは
C:\ti\controlSUITE\device_support\F2807x\v210\F2807x_examples_Cpu1\hrpwm_duty_sfo_v8\cpu01
を私の環境と同じく60KHzのePWM4のみアップダウンカウント ピリオド 500に変更していますが正しく動作しています。
しかしながら、当方の開発中のプログラムにePWM4の設定を全て合わせてもハイレゾは適用されません。
なにが考えられるでしょうか、宜しくお願いします。
トピック: TPS659037の使用方法について
TMDXIDK574の回路図を参考に、TPS659037を使用する回路を
設計しようとしておりますが質問がございます。質問(1)
TMDXIDK574ではJACKよりVMAINを入力すればTPS659037がOnすると認識しております。
認識が正しい場合、VMAINの起動時のTPS659037のOn Requestsの条件は
RPWRON又はPWRONのLow検出でしょうか?質問(2)
+24VからTPS659037用の+5VをDCDC(例えばLM73605)で生成し、
+24Vから+5Vを生成するDCDCのPower GoodをTPS659037のPWRONかRPWRONに接続し
TPS659037をOn/Off制御使用としておりますが可能でしょうか?
もし可能である場合、PWRONかRPWRONのどちらにPower Goodを接続した方が
宜しいか教えて下さい。質問(3)
TPS659037のデザインガイド(SLIA088)では、
SMPS Switch Nodesの出力のコンデンサの合計の容量は
負荷側のコンデンサと合わせ57uF以下で使用することを推奨されておりますが
TMDXIDK574では、CPUのバルクコンデンサを合わせたTPS659037のSMPS Switch Nodesの
出力のコンデンサの合計の容量が57uFを越えております。問題ないのでしょうか?-
このトピックは
maidaが4 年、 10 ヶ月前に変更しました。
-
このトピックは

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page