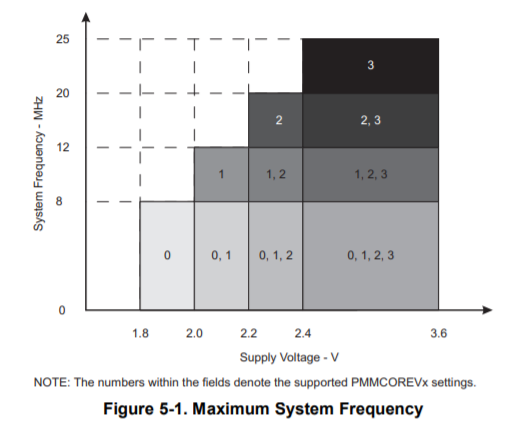-
検索結果
-
トピック: ヘッドフォンアンプの電流制限の考え方
下記BUF634AのデーターシートのP.18 「図39.High-Performance Headphone Driver」と同様の回路でヘッドフォンアンプを検討しています。
その際、推奨するヘッドフォンのインピーダンスを63Ωとしたいのですが、お客様が推奨より小さいインピーダンスのヘッドフォンを接続された場合の出力保護についてご教授いただけないでしょうか。・BUF634Aのデーターシート
https://www.tij.co.jp/jp/lit/gpn/buf634a[回路条件]
電源電圧±10V、ゲイン2、BW オープン、1kHz 4Vp-pの正弦波を入力[Spiceでの測定]
a.ターゲットのヘッドフォン(63Ω)を接続して、出力レベルが最大16Vp-p程度になるようにした場合、出力電流は約±124mAとなりました。(Spiceでの測定値)b.インピーダンス32Ωのヘッドフォンを接続した場合、出力電圧 16Vp-p、出力電流±246mAとなり、まだギリギリOKそうです。
c.インピーダンス16Ωのヘッドフォンにすると、出力電圧5.7Vp-p、出力電流±355mA とBUF634Aの電流制限機能により上下ともクリップした波形となります。[質問]
c.のように、BUF634Aの電流制限機能に依存した使い方をしても問題ありませんでしょうか?
(推奨以外のヘッドフォンなので、音が割れたり音質が低下するのは問題ないのですが、デバイスとして問題ないのか心配)それともインピーダンス16Ωのヘッドフォンを接続しても出力電流が250mA以下になるように、BUF634Aの出力とヘッドフォン端子の間に16Ω程度の保護抵抗を入れて保護した方が良いのでしょうか?
その場合、本来のターゲット63Ω時の出力電力が下がり、アンプとしての出力音圧レベルも下がってしまいますし、より小さな8Ωのヘッドフォンを接続されることを想定すると更に大きな保護抵抗が必要になり、63Ω時の出力音圧レベルも下がる...といったことになり、どの程度まで想定すれば良いのか?ということになってしまいます。
LM3880のデータシートp16に記載されておりますFigure19について質問します。
Figure19では、VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する図がございますが、
VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する回路では、
power-down sequencingが実現不可でしょうか?

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page