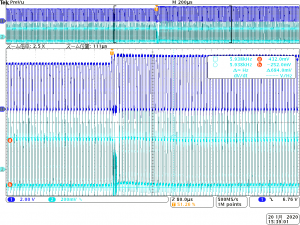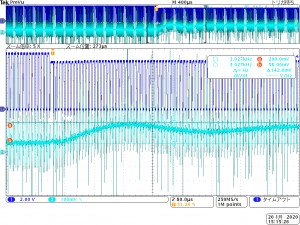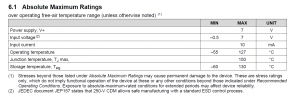-
検索結果
-
トピック: TMP275の絶対最大定格について
TMP275データシート内の絶対最大定格にInput voltage -0.5V~7V とあるが、
SCL,SDAピンにこの値を適用してもよいか教えてください。トピック: A,B同時オンの可否
お世話になります。
UCC21520の使用を検討しております。
動作上、A chとB chの同時オンが必要となるのですが、
典型的なハーフブリッジドライバーを用いた場合、
保護機能が働き、排他動作あるいは同時OFFとなるかと思います。
当該ドライバーでは、このような保護動作なく
A chとB chの同時オンを行うことが可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。-
このトピックは
ETが5 年、 10 ヶ月前に変更しました。
トピック: TPS259230について
TPS259230のOV CLAMP機能について。
本機能の応答速度はどの程度になるでしょうか。
例えば、100ns間、6.1Vを越えるような、
スパイクノイズを、クランプすることは可能でしょうか。トピック: NAND Flashのbadblockについて
ある製品が起動しなくなり,メーカに確認したところ,
MICRON製のNANDフラッシュ:29F1G08ABAEAを使用しており,
NANDフラッシュにバッド・ブロックが発生し,CPUからアクセスができなくなったといわれました。
ある時期まで,正常に動作していたのですが,急にアクセスできなくなりました。質問は,
・バッド・ブロックとはどのようなものか?
・使用しているうちにバッド・ブロックが発生するものなのか?
→発生する場合,どのような要因が考えられるか?(読み込みだけで発生するのか?,書き込みをおこなうと発生?など)よろしくお願い申しあげます。
-
このトピックは

 フォーラム検索:page
フォーラム検索:page